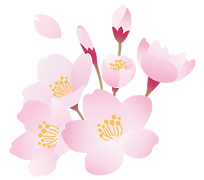サービス案内
介護の不安やお悩みがあるときは、私たちにご相談ください。
何から始めればいいの?


介護保険サービスを受けるための手続きは?
まずはお気軽にご相談ください。

私たち「さくらケアセンター」では、住み慣れたご自宅で安心して暮らし続けられるよう、介護に関する総合的なサポートを行っています。介護は誰もが直面しうる大切なテーマです。不安やお困りごとをひとつでも軽くできるよう、ケアマネージャーがご本人やご家族の想いに寄り添いながら、最適なケアプランをご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
サービス内容
対象となる方は、要介護1〜5と認定された方、介護保険を申請予定の方や、介護の必要性を感じている方(申請サポートも行います)です。


介護に関するご相談対応
要介護認定の申請・更新手続きの代行
ケアプラン(介護サービス計画)の作成
サービス事業所との連絡調整
施設入所や入院時の支援、退院・退所後の調整
家族介護へのアドバイスや支援
そもそも介護保険とは?

介護保険制度は、介護が必要になっても高齢者が住み慣れた地域や自宅でその人らしい生活を続けられるように、また、介護を担う家族の負担を軽くするために、社会全体で支え合う仕組みとしてつくられた制度です。この制度は、国民みんなで保険料を出し合いながら支えるもので、2000年4月にスタートしました。

要介護認定調査とは?
高齢者が介護保険サービスを利用できるようになるためには、「どのくらい介護が必要か」を市区町村に申請し、認定を受ける必要があります。この認定を行うために実施されるのが「要介護認定調査」です。
調査員(市区町村の職員や委託を受けたケアマネジャーなど)が本人の自宅や施設を訪問し、心身の状態や日常生活の様子について聞き取りや観察を行います。調査内容は「歩行の状態」「食事や排泄の自立度」「認知症の有無」「コミュニケーションの状況」など、全国共通の調査票(74項目)に基づいて実施されます。
この調査結果は、主治医の意見書とともにコンピュータによる一次判定、さらに介護認定審査会による二次判定を経て、最終的に「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当(自立)」の認定結果が出されます。
介護保険でどんなサービスが受けられるの?
居宅介護支援のための要介護度ガイド
要介護度の目安と支援内容
要介護 1
-
状態の目安:部分的に介助が必要。歩行や立ち上がりにふらつきがあり、日常生活で一部の支援が必要です。
-
支援内容の例:買い物や掃除の補助、入浴時の見守りや部分的介助。
要介護 2
-
状態の目安:歩行や入浴、排せつなどに介助が必要。外出が難しくなる方もいます。
-
支援内容の例:訪問介護(身体介助)、入浴サービス、デイサービスの利用など。
要介護 3
-
状態の目安:日常生活の多くで介助が必要。認知機能の低下がみられることもあります。
-
支援内容の例:日常的な介護(移動・食事・入浴・排せつ)、短期入所サービスの利用など。
要介護 4
-
状態の目安:ほぼ全介助が必要。立ち上がりや歩行が困難で、認知症の症状が強く出る方もいます。
-
支援内容の例:訪問介護の頻度が増加、夜間の見守り、福祉用具の活用、施設入所の検討。
要介護 5
-
状態の目安:常時介護が必要。寝たきり状態や重度の認知症の方が多く、自力での生活は困難です。
-
支援内容の例:24時間体制の介護サー�ビス、特別養護老人ホームなどの入所支援。

介護保険でレンタルできる用品はある?

介護保険でレンタルできる福祉用具を使うには、まずケアマネジャーに相談し、本人の体の状態や生活環境に合ったものを選ぶことが大切で��す。レンタルできるのは、上記の通り、車いすや電動ベッド、手すりなど限られた品目です。市区町村が指定した事業者から借りる必要があり、費用は原則1割負担(所得により2~3割)です。また、必要ない用具まで借りると自己負担が増えるため、無駄のない利用がポイントです。
介護保険でレンタルできる福祉用具一覧と利用のポイント
対象となる方は、要介護1〜5または要支援1・2の認定を受けている方で、ケアマネージャーの作成するケアプランに基づいて利用可能です。
車いす
特殊寝台付属品
手すり
歩行補助つえ
自動排泄処理装置
車いす付属品
床ずれ防止用具
スロープ(段差解消機)
認知症老人徘徊感知機器
特殊寝台(介護用ベッド)
体位変換器
歩行器
移動用リフト